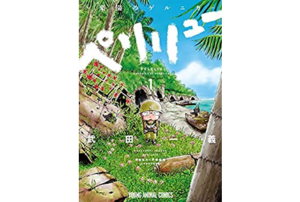「我々は最後のひとりが死ぬまで戦い続けるのだ」
第二次世界大戦の激戦地として知られる、南太平洋・ペリリュー島。圧倒的な戦力差で押し寄せる米軍上陸部隊と対峙し、過酷な防衛戦を繰り広げた日本軍守備隊の物語『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』。悲惨な戦争を真正面から描いた問題作は、ただ読者の胸を痛めるだけでなく、それ以上の“何か”を心の奥底に響かせる。
圧倒的な兵力差の米軍最強部隊を前に……
南太平洋に浮かぶパラオ諸島(パラオ共和国)は、温暖な気候と美しい海に恵まれ、世界的なリゾート地としても知られる。が、主要な島のひとつであるペリリュー島だけは、異端な存在かもしれない。その理由は、現在から75年以上前まで遡る。
第一次世界大戦後から、日本の委任統治領だったパラオ。なかでも南太平洋の重要軍事拠点だったペリリュー島には、10,000人を超える日本軍守備隊が駐留していた。
大海原が広がる南太平洋で貴重な大型飛行場を持つペリリュー島は、戦況が激しくなるにつれ、その存在価値を増していく。
米軍にとって、日本が占領するフィリピン奪還作戦に欠かせない拠点だったペリリュー島。日本軍の一大拠点・トラック島(現在はチューク諸島と呼ばれる)やパラオ本島を制圧した米軍は、1944年・秋に満を持して、ペリリュー島への上陸作戦を開始する。
その数、約5万。上陸部隊の兵力だけでも、日本軍守備隊の5倍以上。激戦地のガダルカナル島を制圧し、米軍最強とうたわれた精鋭部隊・第1海兵師団が、航空機爆撃や艦砲射撃、戦車・重火器など数十倍の火力差で上陸してきたのだ。
美しい楽園の島で倒れていく日本軍兵士たち
物語は、ペリリュー島守備隊・田丸一等兵の視点で語られる。漫画家志望で気弱な青年だった彼は、部隊の日記担当を命じられたことで、冷静な目線で戦場を見つめるようになっていく。
木々と生き物にあふれ、楽園に思えた島を「本当にここが戦場になるのでしょうか」と見渡す田丸。が、爆撃や艦砲射撃でハゲ山と化した島に絶望した彼は、やがて現実を受け入れ……。
「たまたまそこにいて、たまたま(弾に)当たって、死ぬ。ここは戦場で、僕もあんなふうに死ぬかもしれないです」
戦争ものにありがちなリアル描画ではない、デフォルメされた3等身ほどのキャラクターたちが織りなす物語は、凄惨な戦争とはかけ離れた世界のようにも見える。可愛らしいキャラクターたちと、壮大なスケールで描かれる大自然のコントラストが、無意識のうちに現実から目を背けさせるのだろう。
が、次の瞬間、部隊の誰かが簡単に、あっけなく死んでいく。
その度に冷淡な現実へと引き戻される田丸の姿は、読者の心境を映し出す鏡なのかもしれない。お涙頂戴的な創作などなく、淡々と進む物語は、だからこそ悲しく、重苦しい。戦争を美談化しがちな映画やテレビドラマでは描かれない、リアルな戦場がそこにある。

誰も(何も)美化されない真の戦争とは
南太平洋の激戦地といえばガダルカナル島を思い浮かべる方も多いだろうが、約1年半後に勃発したペリリュー島の戦いでは、様々な事情が異なっていた。
もっとも大きな違いは、このペリリュー島防衛戦から、日本軍が“バンザイ突撃”を禁止したことだろう。玉砕を許さず、徹底した持久戦へと戦法を転換したことで、より悲惨な戦闘が長期にわたり繰り広げられることとなった。
事あるごとに田丸を叱咤する鬼軍曹の言葉にも、そうした状況が見え隠れする。
「己の死を恐れるなっ! 恐れるならば国が亡ぶことこそ恐れよっ! 国の家族の平和は今ここにいる我々の戦いにかかってるっ!! 今の自分がやれることをやるのだっ!!」
田丸の理解者で、行動を共にする吉敷上等兵の言葉も切ない。
「僕だって勝って無事に帰りたいんだから。君は、俺らがこの島から生きて帰れると思ってるのかい? もう死ぬ覚悟はできているんだ。でもね、同じ死ぬなら勇敢に戦って立派に死にたいんだ」
誤解しないで欲しいのだが、劇中で何かしらのイデオロギーや主義主張が前面に押し出されることはない。日米ともに、誰も(何も)美化されず、愚か者としても扱われない。登場人物は全員、自分自身と正面から向き合いながら、一日でも長く戦場を生き抜こうとしている。
なので、予備知識がない方でも、すんなりと物語に入っていけるはず。漫画として“とても読みやすい”と評すれば、わかりやすいかもしれない。
が、その分、入り込んだ物語から抜け出すことは難しい。この凄惨な現実から逃れたいと思っても、いっそうズブズブと足が沈み込み……。沼のような作品でもある。
無駄死に。犬死に。そんな言葉が、脳裏に浮かんでは消えていく。戦争とは、何なのか。単純に重苦しい、悲しいといった言葉では片づけられない想いや痛みを、皆さんも『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』から感じ取って欲しい。