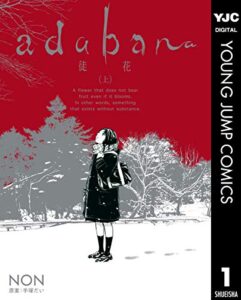『風街のふたり』は、孤独な絵描きの老人と、友だちがいない少女の心の交流を柔らかなタッチで描いたフルカラーコミック。祖父と孫ほどの年の差がありながら、一緒にいることで世界が広がっていく様を、哲学を感じさせる言葉で丁寧にすくい取っている。『メタモルフォーゼの縁側』(鶴谷香央理/KADOKAWA)と並ぶ、年齢差のある2人の友情物語のである本作の魅力を紹介したい。
赤いリンゴやブランケットについたワインのシミが、忘れていたあの記憶を呼び覚ます
1巻には、自宅のアトリエで一人キャンバスに向かってリンゴの絵を描いている老人と、窓の外を駆ける少女のカットに始まり何点か扉絵が収録されているのだが、一枚絵だけでも想像が膨らみ、ドラマを予感させる。趣味のように狂言自殺を繰り返す19歳の少年と、他人の葬式に忍び込むのが趣味のアナーキーな79歳の老女が恋に落ちるアメリカ映画『ハロルドとモード 少年は虹をわたる』(1971年)に魅了された筆者にとって、年齢差や性別を越えて、感性と感性で通じ合える2人の物語は、もはやその設定だけで十分興味を惹かれてしまう。
海辺の街の丘の上に立つ“一等古くて変なおうち”で、猫とニワトリと暮らすヒゲもじゃの老人が、ある日、家の近所の階段に落ちていた赤いリンゴをアトリエに持ち返り、そのリンゴをモチーフに絵筆を走らせる。その間、13ページ目までセリフは一切ないのだが、カットの連なりから老人の穏やかな暮らしぶりが伝わってくる。そこに、「見つけた」という声と共に、ひとりの少女が現れる。リンゴの持ち主だという少女は、躊躇なく老人のアトリエに勝手に上がり込み、キャンバスの絵を見るなり「おじいさんは絵描きさんなの?」「だからこの絵にはリンゴのほんとうが描いてあるんだね」と意味深なセリフを口にする。
初対面にもかかわらず、昔からの知り合いのような馴れ馴れしさで、グイグイ距離を縮めてくる少女。2人はひとつのリンゴを分け合い、屋根の上で流星群を眺めたりもするのだが、他愛もないやりとりの合間に老人の奥底に眠っていた青春時代の記憶がシームレスに紛れ込み、止まっていた時間が動き出す。記憶の呼び水となるのは、少女にもらった赤いリンゴや、久しぶりに引っ張り出したブランケットについていた赤ワインのシミ。それらはまるで、マルセル・プルーストの長編小説『失われた時を求めて』における、紅茶に浸したマドレーヌのような役割を果たしている。
この世の真理に自ら触れた人は、またそれを別の誰かに語りたくなる――
名場面は多々あるが、特に印象的なのが、「スケートをしに行こう!」と少女に誘われ、しぶしぶ付き添った老人が、凍った湖でスケートに興じる楽し気な人々をスケッチしながら、「たった百年後には、ここにいるほとんど全員がいないのだ」と、ふいに達観するシーン。見開きで目の前に飛び込んでくるスケート場は、人々の声さえ聞こえてきそうなほどだが、それを前にしてこの世の真理に触れ、切ない気持ちになる老人に心を寄せずにいられない。
雨漏りするアトリエでコップや花瓶、たらいで雨粒を受けながら、「雨音は雨粒が地上で何かと出会ったときにたてる音だ」「耳を澄ませばこの世界の音が粒立って聴こえてくる。鼓膜のざわめきから、世界は拡張する。今ここに自分が存在する手触りが、ありありとする。耳を澄ましてごらん」と、老人が少女に語りかける場面も忘れがたい。読み手には「雨音は~」という言葉は、若かりし頃の彼自身が見知らぬ老人から聞かされたものであったことが明かされるが、長い間その言葉を忘れず自らの実感として少女に語り継ぐところに、グッときてしまった。人生には「腑に落ちる」瞬間が訪れることを、筆者も知っているからだ。
「世界に馴染めない2人が世界の愛し方を知る物語」とキャッチコピーにある通り、赤いリンゴを介してようやく巡り合えたソウルメイトとも言えるような老人と少女が、互いの感受性を響かせつつ、世界の本質に迫っていく『風街のふたり』。2022年12月には、双葉社から待望の2巻も発売された。小さくとも豊穣なこの物語を、ぜひ堪能してほしい。