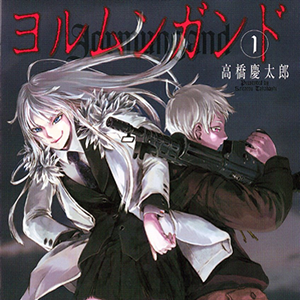「いいね。やっぱいいよヒロト」“何だか楽しそう”なフリーターに降ってきた平屋暮らし
「あんま考えたことないんだよなぁ。『幸せ』とか?」。
お年寄り受けがよく、老婆相手なら口も弾むが、タイプの女性には緊張して何も喋れなくなる……。役者を目指し上京したヒロトは、“タイプの女優を前にNGを連発した”ことでその夢を断念。今は釣り堀でのアルバイトで生計を立てる29歳のフリーターだ。そんな彼には週2回、ひょんなことから仲良くなった年金暮らしの“おばあちゃん”・はなえ宅に上がり込み、夕飯をご馳走になる習慣があった。
「いいね。やっぱいいよヒロト」。
とある晩も好物のトンカツをご馳走になり、カゼ気味ののどに効くからとカリン酒を持たされ、ヒロトははなえ宅を後にする。しかし、2人の交友はこれが最後になった。次の日、はなえがぽっくり亡くなったのだ。それから3カ月後。ヒロトのもとに、美大進学のため上京してきた従妹のなつみがやってきた。これから彼らの2人暮らしが始まる。
ヒロトが身寄りのないはなえから譲り受けた、一戸建ての平屋で。
“なんかいい”自然体な主人公――顧みる「生きづらさ」への向き合い方
今どこに住んで、どんな仕事をして、どんなことを楽しみに、どんな日々を送っているか。その人生設計が一から十まで思い描いてきた通りだと言い切れる人は、そうそういないだろう。流れ流されていたらこうなった、いつの間にかそこに収まっていた、という人が大半ではなかろうか。そして、この先もたどり着く先は“なるようにしかならない”のだろうと思う。真造圭伍の『ひらやすみ』を読んで、ふとそんなことを考える。
散らかった自室に見つけた500円玉で、道すがら好物のたこ焼きを買い込み、幸せそうに報張りながらアルバイトに向かう。本作は、役者になる夢にこそ破れるも、それでもマイペースに楽しそうな日々を送っているらしい主人公ヒロトの、そんなひと幕から始まる。“モラトリアムの権化”とでも言うべき彼の暮らしぶりは、はなえの死に接した際も飾られた遺影のピンボケぶりに口を半開きにして突っ込む姿など、一見するとゆるさばかりが目立つ。
だが、その後平屋になつみを迎えた際、ふと取り出すカリン酒をきっかけにそんなヒロトが急に泣き崩れるシーンがある。そこから、“何となく楽しそうでいいな”くらいの解像度で見えていた彼に、急に奥行きが生まれ、一気に親近感が湧く。誰しも、大なり小なりやりどころのない思いを抱えている。それがふと顔を覗かせる瞬間はあるが、ずっと頭を悩ませているわけでもない。別にそう取り繕っているわけでもなく、それが“ふつう”なのだ。それを体現するヒロトの自然体に想いを寄せつつ、背中を押してもらえるのが本作だ。
この、“なんかいいな”と思えるヒロトに接することで、ふと自分を顧みる時間が生まれ、何となく背中を押してもらう……という瞬間は、作中の登場人物たちにも訪れる。第1巻で象徴的なのは、そんなヒロトの同居人であるなつみのエピソードだろう。なつみはその自意識過剰ぶりで大学デビューに失敗するが、ただ優しいだけではないヒロトのひと言に背中を押され、それをきっかけに不器用なリスタートを切る。何となくやりづらい、生きづらいと思う瞬間は誰にも訪れる。しかし、それは悪いことではない。そう思わせてくれる。
“都会の外れの平屋住みのフリーター”の人生の歩の進め方に想う
“何となくズレている感じ”を肯定してくれる本作が、東京23区の最西端、杉並区阿佐ヶ谷を舞台としているのも、設定の妙だなあと思う。ひと口に“東京23区住み”と括れば連想されやすいラベリングは存在しているが、彼らが「阿佐ヶ谷に生きている」という点にも大きな意義を感じるのだ。“都会の外れの平屋住みのフリーター”を、安直にモラトリアムの真っ最中なのかなと思ってはいけない。彼も日々、彼なりに歩を進めているのだから。