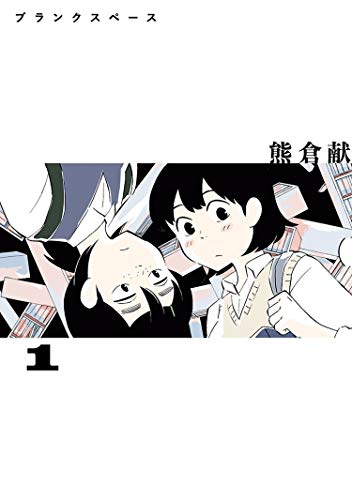
「ドーナツを穴だけ残して食べるには?」その空白に見る無限の可能性
「ドーナツを穴だけ残して食べるには?」という、一見すると馬鹿げた問いかけがある。
ネットサーフィンをしていれば、一度くらいは見かけたことがあるのではないだろうか。
「巨大なドーナツを光速で回転させることにより……」というカタブツな物理派から、「では穴だけ残しますからまずは穴の存在を証明してください」というとんちのきいた一休派まで。「ドーナツを穴だけ残して食べる」ために、各派閥がいかにも言いそうな見解が並ぶ、いわゆる“コピペ”のひとつであるアレだ。
「そんな不可能なことを」と一蹴してしまうこと自体は簡単だが、それでも興味をそそってくるのが、この「ドーナツを穴だけ残して食べる方法」談義だろう。
世の中には、そんなつかみどころのない難問について、専門的知見から真剣に学問した成果をまとめた『ドーナツを穴だけ残して食べる方法 越境する学問−穴からのぞく大学講義』という書籍があったりする。
大阪大学の教授陣による考察を一望できる一冊なのだが、なかでも“精神医学的人間論”からドーナツの穴を考えた井上洋一教授の言葉が面白い。
巨大なドーナツを想像させ、「ドーナツの上を歩いていると考えてみよう」と投げかける井上教授いわく、「ドーナツが持っている無限性の根拠はドーナツの穴にある」。これは、ドーナツは穴があることで、その上を歩く者に終わりのない道を提供できる、という理屈だ。
もしも、穴が塞がれてしまえば、ドーナツはその全貌が分かる=限界が存在する存在となってしまう。一口かじられてしまっても、ドーナツは一定の長さで途切れる=有限となる。
井上教授はこれらの弁を「有限の世界のなかに開いた穴、それが可能性である。私たちはその穴から無限を垣間見ていたいのだろう」と締めくくっている。
「何もないのに…空白なのに でも…あるんだ」空欄JKと空白JKの邂逅
「何もないのに…空白なのに でも…あるんだ」。「クッキーのくり抜いた生地の方とか ドーナッツの穴みたい…」。
“ガールミーツガール”のSFマンガ『ブランクスペース』に登場する、女子高生の狛江ショーコのセリフだ。井上教授の言葉を借りれば、彼女もドーナツの穴に無限を垣間見ている(垣間見ることができる、と書いたほうが正確かもしれない)ひとりと言えるだろう。
だがショーコは、ふとした空想からこういったことを呟いたわけではない。彼女の視線の先には、ドーナツの穴にあるような無限の可能性を本当に現実のものにしてしまう、同級生の片桐スイがいるのだ。
ふたりの友人関係は、ショーコが顔に惚れた男の子に振られテストを空欄だらけで提出した、とある雨の日に始まった。
予報になかった雨に帰り道を急いだショーコは、教科書を濡らさないようにとひと気のない道でショートカットする最中、ぽかんと立ちつくすような光景に遭遇した。それまで目立った交流のなかった地味なクラスメイトのスイが、“透明な傘”で雨をしのいでいたのだ。
“透明な傘”のみならず、「頭の中に部品を思い浮かべ、想像のなかで組み立てることができるものなら、現実に引っぱり出せる」というスイ。“ないのにある”ことにできるその能力を「ドーナッツの穴みたい」と面白がったショーコは、持ち前の明るさとマイペースさで近付き、内気なスイとの距離を縮めていく。
凸凹コンビだからこそ、逆に気が合うのだろう。能力に関するアレコレをふたりだけの秘密としながら、打ち解けたショーコとスイは仲睦まじい高校生活を過ごすことになった。しかし、季節が巡り進級でクラスが分かれると、スイが少しずつおかしな様子を見せるようになる……。
“想像力”が導く“創造力” 「ドーナツの穴」という空白は何をもたらすのか
思うだけなら。考えるだけなら。頭のなかで“ないのにある”こと……「ドーナツの穴」の存在を思い描けるのが、我々の“想像力”だ。ショーコはどうやら、そんな“想像力”の持出した使い手らしいことがうかがえる。
その“想像力”は彼女持ち前のものに高校生という背景も手伝い、とてもたくましい。ショーコの“想像力”の分かりやすい青さに頬がゆるみ、そしてどこか共感するところもあったという読者は、きっと筆者だけではないはずだ。
一方のスイは、そんな誰しもが多かれ少なかれ持つ“想像力”に加えて、いわば“創造力”も有している。「ドーナツの穴」の存在を頭のなかで思い描くだけに留まらず、超常的な理屈で具現化できてしまうのだ。
スイのその“創造力”を肉付けするのも、やはり彼女が送る高校生活である。しかし、作中で描かれるその断面に、明るい“創造力”の種ばかりではなく暗い“創造力”の種も見え隠れするのが、作品に命を吹き込んでいるポイントなのだろう。筆者はそういった描写にも、共感するところのある読者だった。
ショーコとスイは今後、「ドーナツの穴」という無限の可能性に何を見出し、何を始めるつもりなのだろうか。
“創造力”はない以上、良くも悪くも“想像力”を働かせるしかないというのが、第1巻を読み終えた読者のわたしである。












