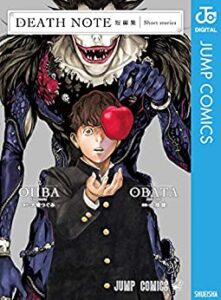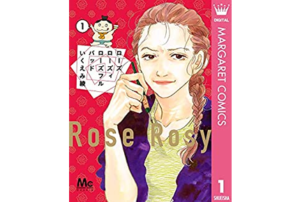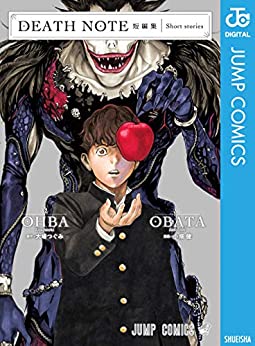
※一部、軽めのネタバレあり
夜神月とLが迎えた結末の“その後”を描いた物語で存在感の強さを痛感
物語の長さが面白さに直結するとは思わないが、個人的に意外と手を出さないのが短編集。短編集とは1話で設定を確立させ、その世界観のなかでキャラクターを生み出してストーリーを展開。そして結末まで持っていくという「読み切りタイプ」の作品が詰め込まれた単行本のことを指す。
オリジナル世界観を扱った短編集もあれば、作者が自身の作品を使ったスピンオフなど形態はさまざま。今回紹介するのは「週刊少年ジャンプ」で連載され、アニメ化や実写映画化、連続ドラマ化されるなど大ヒットを記録した『DEATH NOTE』の短編集。角度の異なる作品が収められているが、まず取り上げたいのが「Cキラ編」だ。本編のその後を描いた作品で、本編のネタばらしから物語がスタートしているので、少数派ではあるとは思うが本編を未読の人は注意した方がいいだろう。
再び日本でデスノート絡みの事件が発生。Lの後継者であるニアは「つまらない殺人犯」と断じて興味を示さないのだが、デスノート所有者を周りが「キラ」と呼ぶことに一抹の不快のようなものを持っている。「キラを認めるわけではありませんが曲がりなりにもキラは~」(単行本P19)というセリフが複雑な心境を如実に表している。
今回のデスノート所有者は老人をターゲットとすることで高齢化社会の諸問題を解決に導こうとしている模様。月は犯罪者を標的にして犯罪撲滅を目指し、作品内では世界の犯罪の7割が減少した言及がある。デスノートの存在が立ちはだかる難題を解決してくれるだけでなく、モブの若者が「生きる権利を主張する奴はごまんといるだろ 死ぬ権利だってあっていいじゃねーか」(単行本P37)と絶叫するなど、ともすると読んでいる者の価値観を大いに揺さぶってくる。こういった描写も『DEATH NOTE』の面白さであり、ハッとさせられる部分でもある。
物語の結末はあっさり目ではあるものの“ならでは”の展開で終幕。ニアがデスノート所有者に対して放つ“とどめの一言”は効果てきめんで、理想と現実、目的と手段、ひいては「生きるとは」といった、人生を懸けて考えるような要素をサラッと盛り込んでいるのはさすが。常に周囲の人物や物語世界に影響を与え続けている月やLのカリスマ性には、改めてうならされた。
デスノートの「新しい使い方」が巧妙で魅惑的
「Cキラ編」のさらに“その後”の世界が舞台となる「aキラ編」。リュークがリンゴほしさに新たなデスノート所有者を探しに行くのだが、デスノート所有者となる田中実の思考回路はなかなかエッジが効いている。
仕掛けについて詳細を書いてしまうとネタバレとなり面白さが半減する可能性がゼロではないが、興味を持ってもらうためにあえて入り口に触れておくと、「もしもデスノートが実際に存在し自分が所有者になったら……?」という“妄想”を、新たな方面から描いたストーリーが繰り広げられる。
キーワードは「オークション」。実が実行したデスノートの使い方は、ある意味で“賢い”使い方の一つかもしれない。正体がばれないように練られた計画についても、ニアが「Lになってから初めて負けました」(単行本P127)と言うほど巧妙さがあり、読んでいてもある種の痛快さが感じられる。
しかも巧妙さは登場人物の実が立てた計画だけではなく、物語の結末に向けた巧妙さという意味でも際立つ。とある“ルールの追加”により実がたどる運命が大きく変わってしまうのだが、彼との約束を“律儀”にリュークが守った結果でもあるのだが、そのあたりの描写はニヒルでリュークのブレなさを示していて、シリーズファンならニヤリとしてしまうことだろう。
デスノートがもし実在したら……?
『DEATH NOTE短編集』には、ほかにも「最初のデスノートの物語「鏡太郎編」」やLの日常や過去を描いた作品なども収録。特に「鏡太郎編」はデスノートの“対極”のようなアイテムも登場したり、ラストカットにブラックユーモアが効いていたりと、また別のカタチの『DEATH NOTE』で楽しませてくれる。
シリーズを共通しているのが、シンプルなアイデアから読者の想像を超える、裏切るような展開と、細部にまでこだわったディテールの緻密さ。思いつくだけなら多くの人ができるかもしれないが、そこからテーマと世界観を壊さずに構築していく行為と内容が、『DEATH NOTE』たらしめている所以と言えるだろう。
デスノートがもし現実世界に存在したら……。使い方によってはなにがしかの問題を一気に解決できる手段となり得ることは、シリーズを通じて描かれている。しかし、それは本当に正しい方法なのだろうか。マンガだからと言ってしまうことももちろんできるが、劇中では感謝する人も存在。これは現実世界においても、さまざまな事象に当てはまる可能性は否めず、簡単に人の生死を描いているようでいて、相対的に命について問いかけられている印象も受ける。
そんなことを考えつつも、エンタメとしては『DEATH NOTE』ならではのスリリングさやシニカルさは健在。改めてデスノートというアイデアに深く、深く感心させられた。